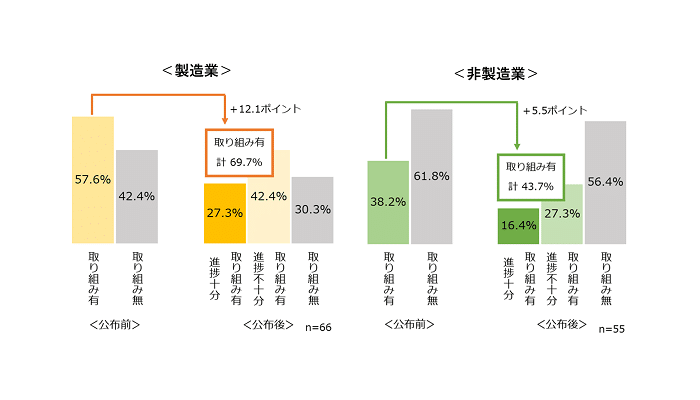複雑化する世界情勢、規制動向、AIテクノロジーが担う役割を解説する本ブログにおいて、経済安全保障の文脈を読み解く上での重要キーワードを「基礎知識編」として随時紹介していきます。
第4回は経済安全保障、とりわけ多国籍企業の組織編成に大きな影響を持つ「デカップリング」について解説します。
米国のトランプ政権下において米中対立の様相が浮き彫りになりましたが、バイデン政権誕生後も対立は継続し長期化が避けられない見通しです。経済面においては、貿易摩擦を皮切りとして技術覇権争いにも発展し、両国が各々経済安全保障を念頭に、輸出管理制度や外国投資規制などを強化しています。このような状況において、国境を越えた自由な経済活動を制限し、対立国を意識して「経済やサプライチェーンのブロック化」*¹を推進することを「デカップリング」と呼んでいます。
デカップリングを推進する中、米国は同盟国などに対しても、中国への情報・技術漏えい阻止を強く要請してきました。日本は2019年に外資による投資などの審査を厳格化する形で外為法を改正しました。これに続く形で、経済安全保障推進法が5月に成立しています。法施行の段階では、「中国などが想定される『安保上の懸念がある国』が関わるサプライチェーンや製品輸出、サービスをどのように管理し、外していくか」*²について、企業はより精緻な判断を下すことが求められるでしょう。