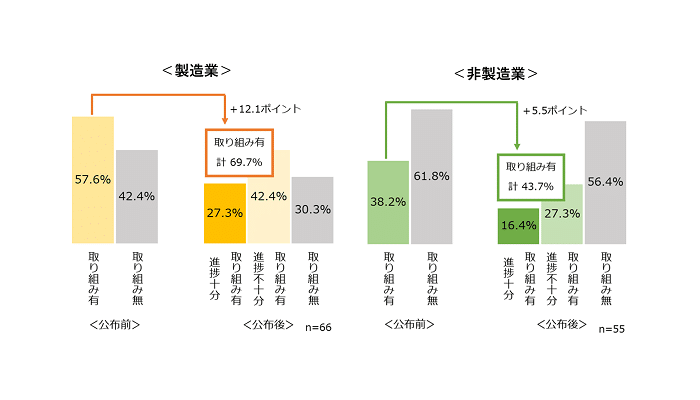導入のメリット2:国境を越えて機密情報を共有し共同研究が行える
日本のメーカーの開発者が諸外国の民間企業と共同研究しようとしても、セキュリティ・クリアランス制度が整っていないため断念せざるを得ない事例も出始めています。最先端の技術は軍民両用の「デュアルユース」の性質を持っているので、欧米諸国が中国などへの技術漏洩リスクに身構えるのも無理はありません。日本では国家機密の管理ルールを定め、漏洩した人に厳罰を科す特定秘密保護法が2014年に施行されましたが、対象となる民間事業者は限定的であり、セキュリティ・クリアランス制度を有している諸外国との連携においては、いまだ不十分な体制です。「統合イノベーション戦略 2020」(2020 年7月 17 日閣議決定)においては「科学技術・産業競争力を最先端レベルで維持するとともに、国際共同研究を円滑に推進し、我が国の技術的優位性を確保・維持する観点も踏まえ、諸外国との連携が可能な形での重要な技術情報を取り扱う者への資格付与の在り方を検討」*²する必要性に言及がなされています。
導入のメリット3:企業のビジネスチャンスの拡大につながる
セキュリティ・クリアランス資格が民間事業の担当者に付与されると、諸外国の政府や企業とのビジネスチャンスの拡大にもつながります。セキュリティ・クリアランス制度を有しない場合、「自動運転に対するサイバー攻撃防御(AI、地図情報、画像解析技術など)」*³について、「ZERODAY情報などがテスラやGMには開示されるがシリコンバレーに出入りしていても日本企業には開示されない」*³可能性が高いというのは痛手です。「電気通信、電気・ガス・石油、重要鉱物、自動車(一部製造業)」といった業種は、セキュリティ・クリアランス制度の法制化によって特に大きな影響を受けると見込まれています。職種別では「リクルーティングや研究開発、オペレーション」*⁴への影響が特に大きいとの見通しです。セキュリティ・クリアランス制度は「ESG投資の機関投資家には、企業の安全保障政策の理解度が重要な判断基準になる」*³という時代の到来を後押しするカギを握っていると言えるかもしれません。
*¹ 2021年9月16日 日本経済新聞出版 國分俊史「経営戦略と経済安保リスク」
*² 2020年7月17日閣議決定 「統合イノベーション戦略2020」
*³ 2020年10月6日 杉田定大「米中新冷戦の中での日本企業の生き残り戦略」
*⁴ 2022年6月2日 日本総研 岩崎海「企業向け 経済安全保障におけるセキュリティクリアランスの活かし方」