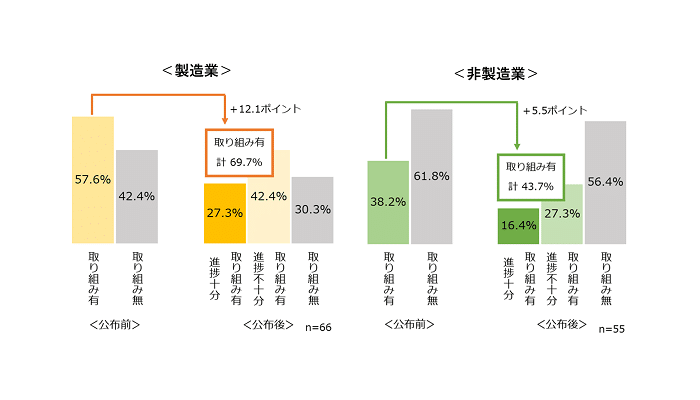2014 年に研究開発費が EU を抜き、世界第 2 位になった中国*²はこの 10 年で大きく成長を遂げ、世界各国における中国との共同研究の可能性が一層広がることとなりました。そのような状況の中、日本において機微技術情報を扱う組織、あるいは機微技術開発に関わる組織にとって、各技術の「主な想定用途」と「実際の利用方法」のギャップが今後さらなる懸念点になることは間違いありません。しかし、どういった技術研究がどのようなバックグラウンドの中国人研究者と共同で行われ、中国軍とどのようなつながりがあるのかを、詳細な解析なしにうかがい知ることはほぼ不可能に近いのが実状です。
機微技術の範疇は幅広い
上記の記事以外でも最近よく耳にする「機微技術」とはいったいどういったものでしょうか?端的に述べると「軍事に用いられる可能性の高い技術」「武器製造などの技術のほか、軍事転用されやすい民生用の技術」を指します。具体的には、オーストラリア政府が以下のような技術を機微技術と分類しています*³。
- 素材分野:先端複合材、ナノ素材
- ロボティクス分野:極超音速機、無人航空機、ドローン、小型衛星
- デジタル分野:AIアルゴリズム、6G、分散型台帳
- バイオ分野:遺伝子工学、ナノロボット、核医学・放射線治療技術
- エネルギー分野:原子力、核廃棄物処理、電力用水素・アンモニア
安全保障上の懸念がある研究機関への技術流出は表玄関からも
軍事分野におけるデュアルユース(軍民両用)の重要性が高まる中で、安全保障上の懸念がある組織による調達活動の多様化・巧妙化が進んでいますが、日本政府も手をこまねいているわけではありません。外為法等で定める規制には、2種類(許可が必要な物の対象が定められている「リスト規制」と、リスト規制の対象外でも兵器開発などに用いられる可能性がある場合許可が必要となる「キャッチオール規制」)が存在し、「規制対象に該当する物の輸出や技術の提供を行う場合には、事前に経済産業大臣の許可」*⁴が求められることとなります。
しかし、規制対象になるかどうかを見抜くのが難しいパターンが多数存在します。以下は実際過去に起こったケースです。
- 「(中国の)西北工業大は19年に米ドレクセル大、韓国科学技術研究院、日本のメーカーとともに新しい電磁波シールド材料の研究成果を発表した。論文では携帯電話を主用途として紹介[中略]こうした素材は一般に『ステルス戦闘機のレーダー吸収材に使われる懸念がある』(笹川平和財団の小原凡司上席研究員)。[中略]西北工業大から参加した2人の教授は中国軍のステルス機の実験を担っていた」*¹。
- 「日本の国立大学や国立研究開発法人に助教授や研究員などの肩書で所属していた中国人研究者9人は、ジェットエンジンや機体の設計、耐熱材料、実験装置などを研究。これらの分野は米中ロが開発にしのぎを削る極超音速兵器の開発で鍵となる技術だという。このうち流体力学実験分野の研究者は、1990年代に5年間、日本の国立大学に在籍。帰国後、軍需関連企業傘下の研究機関で、2017年に極超音速環境を再現できる風洞実験装置を開発。」*⁵。
- 「日本のある省庁は1993~95年、研究開発を日本の電機メーカーに委託した。電機メーカーは研究に関する社内報告書の作成をシンクタンクに委託していた。シンクタンクはさらに、北朝鮮系組織の幹部だった男性が社長を務めるソフトウェア会社に、報告書作成関連業務の一部を委託していた。省庁は[中略]男性の会社に業務の一部が委託されていたことは知らなかったという」*⁶。
機微技術の移転は「産業スパイやサイバー攻撃のような裏口を使った不法なものだけ」*⁷ではありません。プロジェクトでパートナーシップを組む組織や人材のバックグラウンドが把握されていなければ、安全保障上の懸念がある国や機関に「表玄関から堂々と機微技術を」*⁷に移転されてしまう可能性があることに留意する必要があるでしょう。